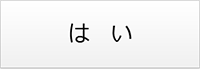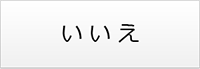2025年度 道教委
「全国学力・学習状況調査 北海道版結果報告書」
に対する北教組声明
2025年11月07日
道教委は11月5日、2025年度「全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書」(以下、「北海道版」)を公表した。文科省は今年度、平均正答率の単純比較を避けるため、結果公表を3段階に分割するとともに、チャート図や箱ひげ図を用いるなど公表方法を変更した。「北海道版」についても同様の変更を行うとともに、これまで北教組が削除を求め続けてきた「管内別結果」についても序列がわかりにくい形となった。しかし報道では7月以降、依然として都道府県や管内(市町村)ごとに「全国(全道)平均を上回ったか、下回ったか」「最も高い管内平均と最も低い管内平均の差」を伝える記事があふれている。道教委は報道機関に対して「序列化や過度な競争が生じることのないこと」を求めているが、結果公表が行われる限り、子どもが競争的な環境に置かれている現状は変わらない。
「北海道版」では、国語、算数・数学、理科ともに全国と大きな差がなく、「正答数の少ない層」の割合も同程度とするなど依然として平均で全国の偏差をみることに終始している。また、ICT活用と平均正答率の関係を示す分析では、必ずしも活用頻度が高いほど正答率が高いと言い切れないにもかかわらず、「ICT推進ありき」の恣意的な分析をしている。
文科省は調査の目的を「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、(中略)教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への学習指導の充実や学習状況の改善等に役立てる」としている。しかし、その目的であれば悉皆調査を毎年行う必要はない。これは、新自由主義的な価値観のもと、機会の均等ではなく結果責任に目を向けさせ、ICT機器の活用など民間業者の参入に誘導するものである。また、学校での学習指導の充実どころか、相変わらず過去問や類似問題を事前に解かせたり、空欄をなくすよう子どもに圧力をかける事例が報告されている。
7月31日に文科省が公表した「全国学力・学習状況調査」の経年変化分析調査(24年度実施)では、3年前の同調査と比較して小学校の国語と算数、中学校の国語と英語の平均スコアが低下しており、特にSES(社会経済的背景)が低い層で下がり幅が大きいことが示された。こうしたことを踏まえ、「全国学テ」の悉皆実施以降、現場がどう変わっていったのか、大局的な分析が必要である。「学力」がテストの結果に矮小化されていることを見逃してはならない。点数をあげるために能率良く正解にたどり着くことをめざし、暗記やテクニックが優先されつつある。また、ICTの活用を目論み、「個別最適な学び」でAIドリルに頼れば、学びは受動的となる。このように現在、理念や法則などの基本概念を身につけることが軽視されつつある。さらに、2017年「学習指導要領改訂」によって標準授業時数および内容が膨大となり、教育課程が過密化するとともに教科書のページ数が増加した。教科書をすべて終えなければならないとの圧力は、理解につまずいている子どもがいても、計画時数通りに授業をすすめることにつながっている。加えて、過密な日課により、かつてのように放課後に補う時間もまったくない。「わからない」を積み上げることで子どもの学びからの逃避は一層すすんでいる。
北教組は、教職員の自発性と創造性を尊重し、子どもが「わかるよろこび」を感じられる学校をめざす観点から、「結果公表」に断固抗議するとともに「全国学力・学習状況調査」の中止と「点数学力」偏重施策の撤回を強く求める。
私たちはこれまでと同様、今後も、憲法・「47教育基本法」・「子どもの権利条約」の理念にもとづく「ゆたかな教育」の実現のため、子どもの主体性・創造性を尊重し、意見表明権を保障した教育実践を積み重ね、市民とともに教育を子どもたちのもとへとりもどすための広範な道民運動をすすめていくことを表明する。
2025年11月7日
北海道教職員組合
道教委2026年度
「公立高等学校配置計画」
および
「公立特別支援学校配置計画」
に対する北教組声明
2025年10月03日
道教委は10月2日、26年度から3年間の「公立高等学校配置計画」(以下、「配置計画」)と26年度の見通しを示した「公立特別支援学校配置計画」を公表した。
「配置計画」では、28年度に①美瑛を募集停止、②釧路商業と釧路明輝を総合学科5学級の新設校として再編統合、③小樽桜陽、苫小牧西、函館西、帯広緑陽、芽室の5校について1学級減、とした。一方で、旭川工業の学級減については、6月の「配置計画案」から変更し26年度に決定とした。また、26年度については、芦別、上川、池田を地域連携校にする、蘭越、虻田、雄武、遠別農業を再編整備留保とし、奈井江商業の募集停止に変更はなかった。27年度については、南茅部の募集停止は変更せず、北見商業の商業科と情報処理科を「情報会計科」に学科転換することで1学級減とした。さらに、25年度入学者選抜の結果により1学級減となった16校のうち、栗山、野幌、千歳北陽、静内、名寄、留萌、美幌、湧別、清水、中標津の10校は間口を維持したものの、芦別、深川西、札幌東豊、伊達開来、枝幸、広尾は1学級減とした。
美瑛については、特色あるとりくみを行うとともに中学校時に不登校を経験した子どもが通い就職へつなげるなど地域の高校として重要な役割を担っているにもかかわらず、入学者20人未満が続いたことや中卒者数の状況などが口実とされた。今年度においても、これまで同様の機械的な募集停止・間口削減を行った道教委の姿勢は断じて容認できない。
26年度から私立高も含め授業料が実質無償化となるが、先行実施している自治体では、公立校離れにともない定員割れした公立校の統廃合がすすんでおり、北海道においても同様となることが懸念される。現に道教委が8月に公表した「高校無償化アンケート」において、中学生の14.9%が進路希望を公立高校から私立高校に見直した。道教委は、高校授業料無償化による公立高校離れに追い打ちをかけるのではなく、今こそ積極的に公立高校の存続に向けた配置計画へと大きく舵を切るべきである。少なくとも、影響を見極めるため、当面は「これからの高校づくりに関する指針(改定版)」(以下、「指針」)の数値基準にもとづいた募集停止・間口削減を見送るべきである。
北教組は、これまで少人数でも運営できる学校形態を確立し地域に学校を残すため、近隣複数校が連携し、1年次は共通科目を地域の校舎で、2年次以降進路希望に応じて子どもが他校舎を行き来できる「地域合同総合高校」を提唱してきた。道教委は、現行の学区を見直すことも視野に圏域協議をさらにすすめるよう促し、これ以上の廃校にならないよう努めるべきである。
「公立特別支援学校配置計画」は、26年度の進学希望見込数を1,502人、定員を全しょうがい児学校(本科)60校で1,788人とし、職業学科を含む知的しょうがい児学校(高等部)24校では、26年度に「道央圏で4学級増」「道北圏で1学級減」と見通した。また、数年後、道央圏で出願者数の増加が見込まれるとした。
中学校卒業者数が減少する中で「特別支援」学校の定員が増加しているのは、「特別支援教育」が分離・別学をすすめている証左であり、「国連障害者権利条約」等に反すると言わざるを得ない。しょうがいが「ある」とされた子ども、保護者が負担を強いられることなく、自宅から通いやすい地元の高校へ通える仕組みづくりこそが必要である。国際的なインクルーシブ教育の理念にもとづき、すべての学校において「合理的配慮」などの教育条件整備、教職員配置を早急にすすめるべきである。
北教組は、引き続き「指針」「配置計画」の撤回・再考を求めるとともに、希望するすべての子どもが地元で学べる「地域合同総合高校」の設置や「私学助成の拡大を求める」署名運動など、子どもの教育への権利と教育の機会均等の保障を実現させるため、道民運動を一層強化していくことを表明する。
2025年10月3日
北海道教職員組合
「給特法」等の一部を改正する法律案成立に対する北教組声明
2025年6月11日
政府は6月11日、教職員の処遇改善と長時間労働の是正を目的として、「公立の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」)」等の一部を改正する法律案(以下、「改正法」)を第217回通常国会において可決・成立させた。
「改正法」の主な内容は、①教職調整額を26年から5年かけて給与月額の4%から10%まで段階的に引き上げる(「給特法」)、②教育委員会に対し教員の業務量管理と健康確保措置を実施するための計画の策定・公表、計画の実施状況の公表を義務付ける(「給特法」)、③新たに教職員間の総合的な調整を行う「主務教諭」を置くことができる(「学校教育法」)、④学級担任手当を想定し義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給する一方で、手当は本給の約1.5%から1.0%に見直す(「教育公務員特例法」)などである。
さらに、衆議院の段階で「修正案」が可決され、これらの本則に附則が加えられた。その主な内容は、29年までに「1ヶ月の時間外在校等時間を平均30時間程度に削減すること」を目標とし、①教育職員1人あたりの担当授業時数削減、②教育課程編成の在り方について検討、③教員定数の標準を改定、③部活動の地域展開を進めるための財政的援助、などの措置を講ずるとするものである。
「改正法」は、「給特法」の基本的な枠組みを維持し、「時間外勤務手当・割増賃金を支給しない」「36協定を必要としない」など、教育職員について労基法の時間外勤務抑制機能を排除するとともに、時間外在校等時間は労基法上の労働時間にあたらず、時間外勤務は「自発的勤務」と評価される重大な問題も放置するものであり、断じて容認できるものではない。
また、「改正法」は、国として業務削減に向けた具体策を一切示すことなく、各教育委員会や学校に「業務量管理・健康確保措置計画」の策定・公表・実施を求めており、何ら実効性を期待できるものではない。むしろ、「不正打刻」や「時短ハラスメント」、「持ち帰り業務」の増加が懸念されるものである。加えて、学校の業務は協力・協働で成り立っていることから、「主務教諭」の新設や学級担任への手当の加算は、すべての教職員の処遇改善策にはつながらず、むしろ教職員の分断を招きかねないものである。さらに文科省は、多学年学級担当手当の廃止とともに、給料の調整額について調整数を1.0から0.5に見直すとしており、処遇改善としても問題があり、不十分である。
このように「改正案」は、何ら実効ある時間外勤務の解消策となっておらず、現場実態の改善が見通せないものであることから、現場を失望させるものと言わざるを得ない。
北海道教職員組合は引き続き、教職員の「長時間労働」の解消と、「なり手不足」「欠員」の解消に向け、①「給特法」の廃止・抜本的見直し、②「学習指導要領」の内容の適正化、標準授業時数の削減、③教職員定数改善、④部活動の社会教育への移行、など制度の抜本的改善を国に求め、地域・保護者・全国の仲間と連帯し、誰もが安心して学び、教えられる学校づくりを実現していく決意である。
以上
北海道教職員組合
第136回定期大会委員長あいさつ
2025年6月27日
北教組第136定期大会の開催にあたり、執行部を代表して一言挨拶を申し上げます。まず、大変お忙しい中、北海道選挙区日政連・北政連勝部賢志参議院議員、日政連古賀ちかげ参議院議員、日教組山﨑書記次長、小川総務部長、連合北海道須間会長、北海道労働者福祉協議会杉山理事長をはじめとした労働福祉事業団体の皆さん、平和運動フォーラム山木代表、道私協教石井執行委員長、地公三者共闘蒲地議長、日中友好道民運動連絡会議古川議長、大築紅葉衆議院議員、池田真紀衆議院議員、河原田英世衆議院議員、北政連議員の皆様をはじめ多数のご来賓の皆様に、本定期大会にご臨席賜りましたことに、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。
さて、最近よく「失われた30年」という言葉を耳にします。1995年に日本経営者団体連盟が「新時代の日本的経営」を発表し、その後数度の労働者派遣法の改悪が行われ、非正規労働者の拡大が推進されていきました。「失われた30年」は、新自由主義が台頭し、市場経済原理が倫理観をかなぐり捨ててなりふり構わなくなっていった期間であり、結果として「貧困と格差」が拡大・固定化した30年と言うことができます。こうした時代の潮流に呼応して教育も大きく新自由主義の影響を受けました。とりわけ、2000年に入ってから「教育改革」が声高に叫ばれるようになり、2006年は、第一次安倍内閣によって教育基本法が改悪され、「国民のための教育」から「国家のための教育」へと変質させられていきました。翌年の2007年には43年ぶりに悉皆による「全国学力・学習状況調査」が復活し、それ以降、点数学力至上主義が跳梁し、短期間での成果を求める成果主義が跋扈するようになりました。このいわゆる「学テ」復活の結果、東京や大阪の都市部を中心に学校選択制が拡大し、各公立校が生き残りを懸けて子どもたちを奪い合う市場的な状況が生じました。また、短絡的に「成果と効率」を求めテスト対策に明け暮れる学校の「塾化」も進行しました。他にも、2007年の「教育関連3法案」の改悪、教員免許更新制の導入など経て、教職員への「査定昇給制度」導入など2006年が大きな曲がり角となり、新自由主義的教育改革が急加速しました。その帰結として、現行の「学習指導要領」は、質・量ともに膨大な内容を求めるものとなるとともに、「何を教えるのか、どのように学ぶのか」から「何ができるようになるか」へと、結果を追求する学習到達度の基準にすり替えられました。文科省は「主体的・対話的で深い学び」を提唱していますが、学校現場は依然として点数学力至上主義の教育観から脱却できておらず、授業展開や指導方法に至るまで画一化がすすむばかりで、「学習スタンダード」と呼ばれる細かい規律で厳しく子どもたちを管理しているのが実態です。このように新自由主義的教育観が浸透した学校現場では、構造的な不平等や格差が不問にされる中で、子どもたちは過度の競争環境に置かれ、常に停滞の許されない直線的な成長を求められるようになるとともに、「自己責任」の意識を内面化させられています。その結果、子どもたちは自己肯定感を高く持つことができにくくなっています。
現在、不登校の子どもは増え続け、小中高合わせて41万人を超え、中学校では15人に1人が不登校となっています。いじめ認知件数も過去最多を更新し続け、およそ73万件に及んでいます。さらには、子どもの自死も527人と過去最多となっています。
これは、教育が新自由主義的価値観に染められるとともに、政治に翻弄され、文科省・道教委がこの30年余り、誤った教育政策を現場に押しつけてきた結果であり、許されません。最近では、「標準授業時数」過多による教育課程の過密化が、子どもたちの疲労度や集中度など学びの質はもとより、教職員の超勤解消の観点からも大きな問題となっており、「学習指導要領」の内容削減とそれにもとづく標準授業時数の削減が不可欠と言えます。教育において「失われた30年」の中で、何が蔑ろにされ、何が失われていったのか。それは一言で言うとゆたかな教育です。主に小中学校では、学びの楽しさを知ること、人と人との関係を築くことが失われていきました。高校・大学では、点数学力の向上とは裏腹に、自ら物事の基本原理や法則・定理などについて深く掘り下げていくこと、あるいはそれを見いだそうとする力が相対的に弱まったと言われています。さらには、すべての段階において創造力や感性を育てる教育が軽視されつつあります。
私たちは、子どもたちの苦悩を受け止め、学校が子どもたちにとって生きづらくなっていることをまず変えて行かなければなりません。そのため、「競争と差別・選別の学校」から、人と人と関係を築きともに学ぶ「共生と連帯の学校」へ、「管理・統制」から「自主・自律の学校」へ、「過密な教育課程」から「ゆとりをもって学べる学校」へと変えていかなければなりません。その中で、社会に関心を持ち、よりよい方向へ変えていこうとする意志を育てる「主権者への学び」をめざして教育実践を強化しなければなりません。
次に教職員をめぐる状況を見ますと、依然として過酷な超勤の常態化は改善されず、このことが世間に浸透したことで、欠員の不補充や教員採用試験の倍率低下など教員のなり手不足が社会問題となっています。こうした中、政府は6月11日、「給特法」等の一部を「改正」する法律案を可決・成立させました。しかし、「改正法」は、「給特法」の基本的な枠組みを維持し、依然として教育職員を労基法の超勤抑制機能の埒外に置くとともに、時間外在校等時間は「自発的勤務」と評価される重大な欠陥を放置するものであり、断じて容認できません。また、国として業務削減に向けた具体な方策を一切示しておらず、各教育委員会や学校の努力のみに頼るものとなっています。これでは時間外在校等時間の削減は全く期待できず、むしろ、「不正打刻」や「時短ハラスメント」「持ち帰り業務の増加」が懸念されます。北教組は今後も、①「給特法」の廃止・抜本的見直し、②「学習指導要領」の内容削減とそれにもとづく標準授業時数の削減、③教職員定数改善、④部活動の社会教育への移行、など抜本的な超勤解消策を求め、全力でとりくんでいきます
今年は戦後80年の節目を迎える年です。しかし、世界情勢は混迷を極めており、理想とはかけ離れた現実が表れています。ロシアによるウクライナ侵攻から3年余りが経過しましたが、依然として収束していません。イスラエルによるガザ攻撃は、1年半以上経過してもなお熾烈さを増しています。ガザでの死者は5万5千人を超えました。このうち約2万人が子どもたちで、ジェノサイドの様相を呈しています。さらには、イスラエルとイランの武力攻撃の応酬に加え、米国によるイランの核関連施設への攻撃までが行われ、きわめて危機的・緊迫した状況となっています。
こうした中、昨年の日本被団協のノーベル平和賞の受賞は一縷の光となりました。代表委員の田中さんは、授賞式におけるスピーチの中で、「その時目にした人々の死にざまは、人間の死とはとても言えないありさまでした。(中略)たとえ戦争といえどもこんな殺し方、こんな傷つけ方をしてはいけないと、私はそのとき、強く感じたものであります」と述べました。その上で、「核兵器の非人道性を感性で受け止めることができるような原爆体験の証言の場を各国で開いてください」「核兵器は人類と共存できない、共存させてはならないという信念が根付くこと、自国の政府の核政策を変えさせる力になることを私たちは願っています」と演説されました。私は、田中さんが何故「理性」ではなく「感性」という言葉を使われたのか、気になっていました。社会的動物である所の生物種たる人は、人の道に反するか否かの根源的なことについては、確かに「感性」で受け止めているものだなどと漠然と考えました。その後、ガザで活動を続ける「国境なき医師団」の萩原さんの新聞記事を読んだ際に、自分なりに納得できる答えが見つかりました。その記事の中で、萩原さんは、「ガザで起きていることは、私が知るこれまでの活動と比べても、人道や尊厳という言葉の一線を、はるかに越えている状況」とした上で、「私の活動の根源には怒りがあるのは確かです。怒りはあるのですが、自分は自分にできることをやるしかない」と述べていました。この記事を読んで、被団協の田中さんが「感性」という言葉を使ったのは、人が人の道に反する出来事を身をもって体感した後に、たとえ困難の中にあっても、あるいは困難であるとわかっていても何か行動を起こそうとする、その力の源泉は決して「理性」と表現できるものではなく、「感性」と呼ぶのが相応しいものであり、「感性」で受け止めることが人に信念を持たせ行動につながると考えたからではないかと思いました。その上で、先の大戦などで戦争を経験した人々は、戦争の非人道性を感性で受け止め、「戦争は絶対にいけない」と信念を持ち、戦後日本の平和の礎を築いてきたのではないかと思い至りました。私は、批判的思考力とともに、こうした「感性」を育て大事にする教育こそが今最も重要なのではないかと思っています。先ほど紹介したガザで活動している「国境なき医師団」の萩原さんの記事では、「そんな日々でも、子どもたちはやはり希望だった」と記されています。子どもたちは、如何なる状況にあっても、私たちの希望であり、光なのです。北教組は、「教え子を再び戦場に送らない」の信念を強固なものにして、どんなに厳しい状況が前に立ち塞がっていても、子どもたちのために、それぞれができることをする仲間の集団であり続けたいと思います。
最後に、7月20日に投開票が予定されている第27回参議院議員選挙では、教育の議席を守るため比例区・日政連「水岡俊一」さん、北海道選挙区・日政連・北政連「勝部けんじ」さんの再選に向け、現退一致で北海道教育フォーラムに結集して全力でとりくんでいくことを誓い、開会にあたっての挨拶に変えさせていただきます。ともに頑張りましょう。
「給特法」等の一部を改正する法律案成立に対する北教組声明
2025年6月11日
政府は6月11日、教職員の処遇改善と長時間労働の是正を目的として、「公立の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」)」等の一部を改正する法律案(以下、「改正法」)を第217回通常国会において可決・成立させた。
「改正法」の主な内容は、①教職調整額を26年から5年かけて給与月額の4%から10%まで段階的に引き上げる(「給特法」)、②教育委員会に対し教員の業務量管理と健康確保措置を実施するための計画の策定・公表、計画の実施状況の公表を義務付ける(「給特法」)、③新たに教職員間の総合的な調整を行う「主務教諭」を置くことができる(「学校教育法」)、④学級担任手当を想定し義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給する一方で、手当は本給の約1.5%から1.0%に見直す(「教育公務員特例法」)などである。
さらに、衆議院の段階で「修正案」が可決され、これらの本則に附則が加えられた。その主な内容は、29年までに「1ヶ月の時間外在校等時間を平均30時間程度に削減すること」を目標とし、①教育職員1人あたりの担当授業時数削減、②教育課程編成の在り方について検討、③教員定数の標準を改定、③部活動の地域展開を進めるための財政的援助、などの措置を講ずるとするものである。
「改正法」は、「給特法」の基本的な枠組みを維持し、「時間外勤務手当・割増賃金を支給しない」「36協定を必要としない」など、教育職員について労基法の時間外勤務抑制機能を排除するとともに、時間外在校等時間は労基法上の労働時間にあたらず、時間外勤務は「自発的勤務」と評価される重大な問題も放置するものであり、断じて容認できるものではない。
また、「改正法」は、国として業務削減に向けた具体策を一切示すことなく、各教育委員会や学校に「業務量管理・健康確保措置計画」の策定・公表・実施を求めており、何ら実効性を期待できるものではない。むしろ、「不正打刻」や「時短ハラスメント」、「持ち帰り業務」の増加が懸念されるものである。加えて、学校の業務は協力・協働で成り立っていることから、「主務教諭」の新設や学級担任への手当の加算は、すべての教職員の処遇改善策にはつながらず、むしろ教職員の分断を招きかねないものである。さらに文科省は、多学年学級担当手当の廃止とともに、給料の調整額について調整数を1.0から0.5に見直すとしており、処遇改善としても問題があり、不十分である。
このように「改正案」は、何ら実効ある時間外勤務の解消策となっておらず、現場実態の改善が見通せないものであることから、現場を失望させるものと言わざるを得ない。
北海道教職員組合は引き続き、教職員の「長時間労働」の解消と、「なり手不足」「欠員」の解消に向け、①「給特法」の廃止・抜本的見直し、②「学習指導要領」の内容の適正化、標準授業時数の削減、③教職員定数改善、④部活動の社会教育への移行、など制度の抜本的改善を国に求め、地域・保護者・全国の仲間と連帯し、誰もが安心して学び、教えられる学校づくりを実現していく決意である。
以上
北海道教職員組合